
自宅の生活音が気になったり、ピアノなどの楽器の演奏をするために、防音対策を検討する人も多いでしょう。防音のためのリノベーションが出来ることは知っているものの、気になるのが費用の問題ではないでしょうか。
この記事では防音工事の種類とその費用相場、費用を抑えるポイントについて解説します。生活における「音」が気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。
防音工事は目的によって施工内容が変わる

防音工事を計画する際は、目的の整理から行いましょう。外部からの音を遮断したいのか、それとも室内からの音漏れを防ぎたいのか、その目的によって必要な対策は大きく異なります。
たとえば、ピアノやギターといった楽器の演奏など、大きな音を出す場合は、天井・壁・床を含めた本格的な防音工事が必要です。大きな音は、音がさまざまな経路で伝わるため、一箇所だけの対策では十分な効果が得られないことが多いです。
一方、生活音レベルであれば、窓の改修や床材の変更など、部分的な対策で十分な場合も多くあります。道路からの騒音が気になる際は窓の防音性能を上げる、足音などが階下に伝わるのを割けたい場合は床や防音工事で改善が期待出来ます。
防音工事の種類とそれぞれの費用相場

防音工事には壁や床、窓、天井、そして防音室の設置など、さまざまな種類があります。それぞれの工事内容と費用相場について、詳しくみていきましょう。
壁の防音工事(15~30万円/1面)
壁の防音工事は、遮音材や吸音材を設置して音の伝達を軽減する工事です。工事方法は大きく分けて、既存の壁に防音材を追加する方法と、壁を解体して防音材を入れ替える方法があります。
既存の壁に防音材を設置する場合、工事費用は1面あたり15~30万円程度が目安となります。金額は壁の大きさや使用する防音材の種類によって変動しますし、高性能な防音材を使用する場合は、さらに高額になる可能性はあります。
また、壁に設置された換気口も音漏れの原因となるため、必要に応じて防音換気口への交換も2~5万円程度の費用で実現可能です。
床の防音工事(5~80万円)
床の防音工事も、抑えたい音の種類や大きさによって必要な対策が異なります。生活音程度の軽い音であれば、フローリングの張り替えやカーペットの敷設など、比較的簡易な工事で対応可能です。
床材の張り替えだけの簡易的な工事の場合、費用は5~25万円程度となります。特に、遮音性能の高いフローリング(例:LL-40やLL45レベルの遮音フローリング)を選ぶと効果が高まるでしょう。ただし、重い音や大きな振動を抑える必要がある場合は、床下に防音材を設置する本格的な工事が必要となるため、30~80万円程度の費用がかかります。
窓の防音工事(5~15万円/1箇所)
窓の防音工事には、防音ガラスへの交換と二重窓の設置という2つの主な方法があります。防音ガラスは、通常のガラスよりも厚みがあり、複数のガラスの間に空気層を設けた特殊な構造が特徴です。この構造により、外部からの音の伝わりを大幅に軽減できます。
既存の窓を防音ガラスに交換する場合、1箇所あたり5~15万円程度の費用が必要です。一方、二重窓を設置する場合も同程度の費用となるものの、防音効果に加えて断熱効果も得られるほか、省エネ関連の補助金が利用できる可能性もあります。国や自治体などがおこなっている支援制度もないか、確認してみてもいいかもしれません。
二重窓の設置は、特に外部からの騒音対策として効果的です。また、既存の窓を活かしたまま設置できるため、工事の手間も比較的少なくて済むでしょう。
天井の防音工事(40~80万円)
天井の防音工事は、階上の住人に音で迷惑をかけないために行われます。天井にも壁と同様に遮音材や吸音材を使用します。天井一面の工事の場合、40~80万円程度の費用がかかるほか、あまり重い素材を設置すると落下事故の危険性があるため、慎重な施工が必要です。
防音室の工事(50~500万円)
防音室の設置は、本格的な防音対策のひとつです。ユニット型の防音室を設置するか、部屋全体を防音仕様に改修するかの2つの選択肢があります。
ユニット型防音室の設置費用は、サイズや性能によって50~250万円程度となります。これに対し、部屋全体を防音室に改修する場合は150~500万円程度かかります。費用の差は大きいものの、用途や必要な防音性能によってどちらが適しているか考える必要があるでしょう。
たとえば、楽器練習用の防音室では、音の種類や大きさに応じた適切な防音性能が求められます。ドラムなど大きな音を出す楽器の場合は、より高い防音性能が必要となり、それに応じて費用も増加します。
防音工事を行う際の注意点
防音工事を行う際に、注意したい点は以下の通りです。
施工業者を選ぶ
防音リフォームの成否は、施工業者のアフターフォローの体制が整っているか、保証内容はどうなっているかなども大切な判断材料となります。見積書の内容を細かく確認し、使用する材料や工法について丁寧な説明ができる業者を選ぶようにしましょう。
近隣への配慮
防音リフォーム工事中は、騒音や振動が発生することがあります。特にマンションでは、管理組合への届出や承認が必要となる場合があるため、事前に確認しておきましょう。また、工事可能な時間帯についても管理規約で定められていることがあります。
建築基準法を確認する
特に大規模な防音リフォームを行う際は、建築基準法に適合しているかどうかや、場合によっては、建築確認申請が必要になることもあります。また、防火区画や避難経路に影響を与える工事の場合は、法令に従った設計や施工が求められるなどもあるため、事前に施工業者や建築士などの専門家に相談することをおすすめします。
マンションでの工事は専有部分のみ
マンションでは、原則として専有部分に限っての実施になります。共用部分である外壁や床スラブ、共用の配管などには工事を行えないため、防音対策の選択肢が限られることがほとんどです。
たとえば、床の防音工事では、既存の床材の上に防音材を敷くことはできますが、マンションの構造体に直接手を加えることはできません。同様に、壁の防音工事でも、躯体に影響を与えない範囲での施工となります。
このため、マンションで防音工事を計画する際は、管理規約をよく確認し、実施可能な工事の範囲を把握しておく必要があります。また、工事内容によっては管理組合の承認が必要となる場合もあるため、工事後のトラブルを防ぐためにも、事前に相談することをおすすめします。
防音工事の費用を安く押さえるには?

防音工事の費用を少しでも抑えたい!という方は、以下のポイントをチェックしてみると良いです。
部分的な防音対策を検討する
防音工事の費用は工事範囲によって変動するため、目的に対して必要な部分だけ施工すると良いです。特に生活音レベルの防音であれば、窓の改修や床材の変更などの部分的な対策で十分な効果が得られることが多いので、目的と対策が合っているかを見直してみましょう。
このように必要な箇所に絞って改修すると、全体的な防音工事の費用を抑えられます。
また、DIYや既存の家具や装飾品を工夫することでも防音効果を高めるといった方法もあります。窓に厚手のカーテンを設置したり、床にカーペットを敷くなど、音の反響を軽減させることで、大掛かりな工事をせずとも、十分な防音効果を得られる場合があります。
補助金や助成制度を活用する
二重窓の設置など、断熱効果のある工事については、住宅省エネ関連の補助金が利用できる場合があるので、各自治の情報を事前に調べてみましょう。
2024年11月22日以降に対象工事に着手し、2025年12月31日までに工事が完了するもので、一戸あたり5万円から最大200万円まで補助が受けられる
複数の業者から見積を取る
防音工事に限ったことではないですが、複数の業者から見積を取り比較検討をすることで、費用負担の軽減に繋がる場合があります。同じ工事内容でも、業者によって費用に差が出ることがあるため、見積時に以下の点を確認するとよいです。
勿論、費用だけでなく技術やアフターフォロー含め総合的に判断し、費用対効果の高い提案を選んだ方が、満足度は高くなります。
防音工事後の維持管理について

防音工事をしても経年することで徐々に劣化し効果が薄れていってしまいます。定期的な点検とメンテナンスを行うことで、防音効果をより長く保ち続けることができます。
定期的な点検
一般的な防音材は、通常5~10年以上は劣化することはありませんが、1年に1度程度、ひび割れや剥がれがないかを目視でチェックすることをおすすめします。また、窓や扉の気密パッキンの劣化や隙間がないかも確認しましょう。隙間ができると防音効果が低下するため、パッキンの交換やシーリング材の補修を検討するとよいでしょう。
メンテナンスについては、使用されている防音材の種類によって適切な方法が異なります。たとえば、防音シートは定期的に表面の清掃を行い、防音パネルは軽く押して固定されているかを確認すると安心です。不具合を発見した場合は、早めに補修や交換を検討しましょう。
| 劣化の種類 | 確認ポイント | 影響 | 推奨対策 |
|---|---|---|---|
| ひび割れ・剥がれ(防音シート、壁面防音材) | シートやパネルが浮いていないか、壁との隙間がないか | 防音効果低下、音漏れ発生 | 剥がれた部分の補修、部分的な貼り替え |
| スポンジ系・吸音材の劣化(ウレタン材など) | 変色、硬化、弾力低下 | 吸音性能の低下、反響増加 | 劣化部分の交換 |
| 気密パッキンの劣化(窓・ドア) | 隙間ができているか、パッキンが変形・ひび割れしていないか | 防音効果低下、隙間風発生 | 新しいパッキンに交換 |
| 防音パネルの固定緩み | ネジや接着剤の固定が弱くなっていないか | 音の振動が伝わりやすくなる | 再固定、ネジの締め直し |
効果を持続させるための対策
密閉性の高い防音室では、結露やカビの発生を防ぐため、定期的な換気を行いましょう。
結露が発生すると防音材の劣化を早める原因となるほか、カビの発生にもつながります。室内の温度と湿度をこまめにチェックし、必要に応じて除湿器を使用するなどの対策を取ると良いです。
また、メンテナンスも自分で出来る範囲と業者にお願いするものがあるので、下記を参考に検討してみてください。
| 作業内容 | DIY可能 | 費用目安(業者依頼) |
|---|---|---|
| 防音シートの補修 | ◯ | 2~5万円(部分補修) |
| 防音シートの全面交換 | ×(広範囲なら業者推奨) | 15~30万円 |
| 吸音材の交換 | ◯(貼り替え) | 5~10万円 |
| 窓・ドアのパッキン交換 | ◯ | 1~3万円 |
| 防音パネルの再固定 | ◯ | 3~8万円 |
まとめ
.jpg)
防音工事の費用は、規模によって数万円台から数百万円まで変動します。費用を軽減しつつ効果的な施工をするために、専門家に相談し最適な防音計画を立てることをお勧めします。
「カウカモ」では、一点ものの住まいを求める人に向け、厳選した中古・リノベーション物件を紹介しています。理想の部屋に住みたいと考えている方は、ぜひカウカモのウェブサイトをご覧ください。
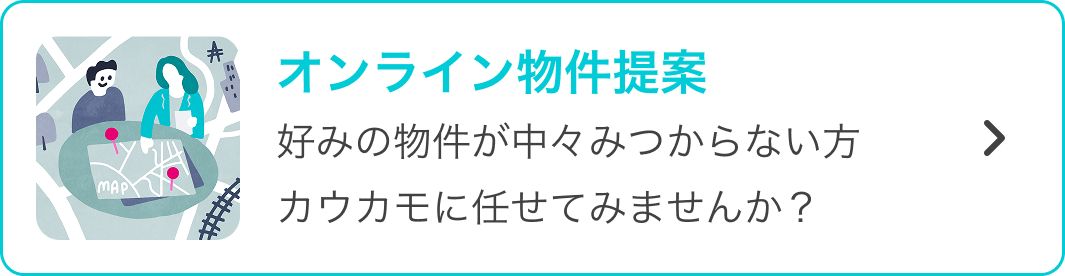

中古・リノベーションマンションの流通プラットフォームに関する知識をわかりやすく提供するため、カウカモ(cowcamo)で日々勉強中。築古マンションの魅力とリノベーションのメリット・デメリットについて深く学び、読者の皆様が最適な選択をできるようサポートしたいと考えています。最新の住宅トレンドや資産価値の維持に関する情報も発信していくので、ご期待ください。

琉球大学大学院理工学部卒。環境建設工学を専攻し、大学院卒業書、建築設計事務所に勤務し、住宅や公共施設など様々な建物の設計に携わる。現在は建築デザイナーとして不動産開発の企画・設計から運営まで行うコンサル会社にて、オフィス設計やリノベーションなどを中心に手がける。趣味は街歩きと珈琲焙煎。空き家を活用して設計事務所と珈琲屋さんを開くことが目標。

















