
近年の住宅設計では、収納と動線を効率的に組み合わせた「ウォークスルークローゼット(WTC)」を取り入れる事例が増えつつあります。
ウォークスルークローゼットは、クローゼットを通り抜けて別の空間へ移動できる構造が特徴で、回遊性を高めながら収納スペースを有効活用できる点が魅力です。一方で、動線が長くなったり、収納力が十分でないと感じる場合もあり、間取りによっては使いにくさを感じることもあります。導入を検討する際は、メリット・デメリットの両面を把握しておくと安心です。
この記事では、ウォークスルークローゼットの基本的な特徴から具体的なプランの考え方まで、設計時に役立つポイントをまとめています。
ウォークスルークローゼットとは

ウォークスルークローゼットは、2か所の出入り口を持つことで、部屋同士や部屋と廊下を回遊できる動線をつくる収納スペースです。
たとえば寝室と洗面所の間に設ければ、移動の途中で着替えや収納ができるため、行き来の手間が減り、動線がスムーズになります。
マンションなどでは収納スペースが限られることが多く、住戸面積に対する収納率は10%前後が一般的とされています。そのため、ウォークスルークローゼットを取り入れることで、限られた空間を効率よく活用できます。
このように回遊性をもたせた間取りにするには、生活動線を意識した設計がポイントになります。
ウォークインクローゼットとの違い

ウォークインクローゼット(WIC)とウォークスルークローゼット(WTC)は、出入り口の構造が異なります。WICは通常、1つの出入り口を持つ収納空間で、WTCは2つの出入り口があり、通り抜けが可能です。
従来のウォークインクローゼットは出入り口がひとつで、収納に特化した行き止まり型の空間です。同じ面積でも、ウォークスルークローゼットは通路の役割も果たすため、収納専用スペースとして使える面積はやや少なくなる傾向があります。
一般的にウォークインクローゼットには、換気設備が設置され、棚板やハンガーパイプが備えられています。収納スペースとしての役割が強いため、納戸と似た機能を持つとも言えます。寝室に隣接している間取りが多く、プライベートゾーンに立ち入られる可能性が低いのがメリットです。
一方、ウォークスルークローゼットは、収納と通路の役割を持ち、2か所の出入り口から通り抜けができます。ウォークスルークローゼットは、通り抜けできる構造によって回遊性が向上するため、通気性や収納アクセスの利便性が高くなる一方で、間取りによっては入ってほしくない部屋とつながる場合もあるため、プライバシーの確保が必要になることもあります。
ウォークスルークローゼットのメリットと活用例

ウォークスルークローゼットには、住空間の回遊性を高め、家事動線を効率化できるというメリットがあります。2か所の出入り口によって自然な通気が促されるため、収納物の湿気を抑え、カビの発生リスクを軽減する効果も期待できます。扉を設けず開放的にすることで、光が入りやすく、明るく清潔感のある空間に仕上がるのも特長です。
活用例①:ファミリークローゼットとして使う
ウォークスルークローゼットは、ハンガーパイプや棚を両側に設置できる幅広のレイアウトが可能なため、一般的な収納よりも容量を確保しやすく、家族全員の衣類をひとつの空間にまとめて管理できます。洗濯物を各部屋に運ぶ必要がなくなり、「たたむ→しまう」の家事動線を短縮できるのも大きな利点です。
活用例②:玄関とリビングをつなぐ土間収納として使う
玄関からリビングへ抜ける動線上にウォークスルークローゼットを設け、靴のまま使える土間収納として活用するケースです。子どもの外遊び道具やベビーカー、スポーツ用品など、外で使うものをまとめて収納できるほか、コートを掛けておけば花粉やホコリの室内への持ち込みも防げます。忘れ物をしても靴を脱がずに取りに戻れるのも便利なポイントです。
ウォークスルークローゼットのデメリット

ウォークスルークローゼットには多くの魅力がありますが、設計や使い方によっては注意すべき点もあります。
設置にある程度のスペースが必要
通路と収納を両立させるため、限られた面積では間取りに組み込みづらいケースがあります。
冷暖房の効率が下がることがある
隣接する複数の部屋をつなぐ構造のため、ウォークスルークローゼット単体で温度調整を行うのが難しい場合があります。
整理整頓が前提になる
動線上にある収納のため、物が多すぎたり散らかったりすると、通りづらくなってしまいます。すっきりと使いこなす工夫が求められます。
プライバシーを重視する使い方には向かない
着替えや見せたくない収納には、壁面収納やウォークインクローゼットなど、より閉じた構造の収納の方が適していることもあります。
ウォークスルークローゼットの配置パターン

ウォークインクローゼットやウォークスルークローゼットには、収納の配置に応じて I型(片側収納)・II型(両側収納)・L型(コーナー収納)・U型(3面収納)といった基本的な形状パターンがあります。
このうち、ウォークスルークローゼットは、出入り口が2か所ある「通り抜け型」の収納スタイルです。なかでも I型・II型は動線に組み込みやすく、ウォークスルーとして一般的です。
L型・U型なども設計次第で導入可能ですが、通り抜け構造には工夫が必要となります。
I型:片側収納タイプ
I型は、壁の片側に収納を配置したシンプルなレイアウトです。限られたスペースでも導入しやすく、動線を妨げない点が特長です。
必要スペースの目安は、収納部分の奥行50~60cmと通路幅60cm以上を合わせて、幅約120~182cm、奥行約120cm程度。収納量は比較的少なめなので、使う物を厳選した整理が求められます。
II型:両側収納タイプ
II型は通路の両側に収納を設けるタイプで、限られた面積でも収納量を最大化できる設計です。収納奥行に加えて広めの通路幅が必要なため、幅120~182cm、奥行180cmほどのスペースを確保できると安心です。おおよそ畳2畳分が目安です。
L型:コーナー収納タイプ
L型は、コーナー部分を活用して直角に2面の収納を配置するタイプです。収納量はI型より多く、分類しやすいのも特長です。玄関とリビング、洗面所の間に設けるケースが多く、動線を90度に折って配置することで、空間に合わせた効率的なレイアウトが可能です。スペースは180cm以上の幅があると使いやすくなります。
U型:3面収納タイプ
U型は、三方向を収納で囲んだ形式で、最大級の収納量を確保できます。収納空間として独立性が高く、寝室に隣接させれば着替えスペースとしても活用しやすくなります。間取りによっては通り抜けにならない場合もあるため、動線計画とセットで検討することが大切です。
失敗しないための4つの注意点

ウォークスルークローゼットの設置で失敗しないためには、以下の4つを考慮する必要があります。
ここでは、それぞれの注意点について解説していきます。
整理整頓を習慣化する
通り抜けできる構造を活かすためには、通路に物があふれないよう、常に整理された状態を保つことが大切です。収納する物の量をあらかじめ決めておき、それを超えそうになったら見直すようにすると、快適な状態を維持できます。
水回り近くの換気対策をする
水まわりに隣接してウォークスルークローゼットを設ける場合は、湿気によるカビや収納物の劣化に特に注意が必要です。可能であれば、水まわりからは距離を取るか、配置をずらすことを検討すると安心です。
設置が避けられない場合には、24時間換気の確認に加え、除湿器や調湿材を併用して湿気対策を行いましょう。
十分な収納スペースを確保する
ウォークスルークローゼットでは、収納量だけでなく、通路としてのスペースを確保することも必要です。通路幅は最低でも60cm、できれば70cm程度あると、物の出し入れや人の通行が快適になります。
引き出し式の収納ケースを設置する場合は、開閉時に体が入れるスペースがあるかも含めて、実寸での確認が大切です。設計段階で生活動線をふまえ、「どこに、どれだけの収納を、どう配置するか」まで検討しておくと、暮らしやすさにつながります。
まとめ

ウォークスルークローゼットは、収納と動線の機能を兼ね備えた設計で、回遊性が高く、家事や生活の動線を短縮できるのが特長です。
一方で、設置場所やレイアウトによっては使いにくく感じることもあるため、設計時には動線と収納量のバランスを意識して、型や広さを検討することが大切です。
「カウカモ」では厳選した中古・リノベーション物件を紹介しています。ウォークスルークローゼットが設置されている物件も掲載されることがあるので、ぜひカウカモのウェブサイトをチェックしてみてください。
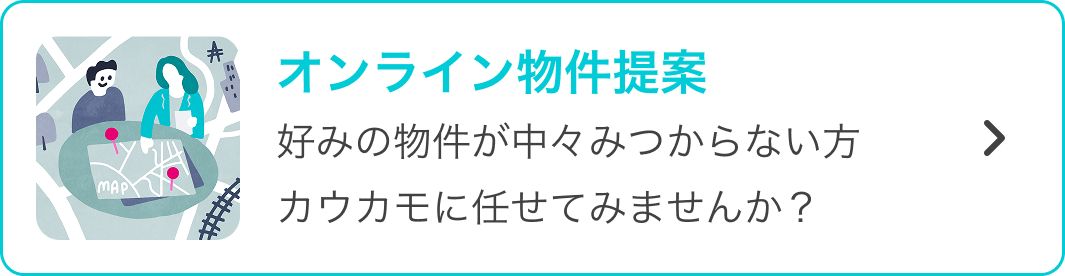

中古・リノベーションマンションの流通プラットフォームに関する知識をわかりやすく提供するため、カウカモ(cowcamo)で日々勉強中。築古マンションの魅力とリノベーションのメリット・デメリットについて深く学び、読者の皆様が最適な選択をできるようサポートしたいと考えています。最新の住宅トレンドや資産価値の維持に関する情報も発信していくので、ご期待ください。

琉球大学大学院理工学部卒。環境建設工学を専攻し、大学院卒業書、建築設計事務所に勤務し、住宅や公共施設など様々な建物の設計に携わる。現在は建築デザイナーとして不動産開発の企画・設計から運営まで行うコンサル会社にて、オフィス設計やリノベーションなどを中心に手がける。趣味は街歩きと珈琲焙煎。空き家を活用して設計事務所と珈琲屋さんを開くことが目標。

















