
マンションは一般的に「建物の高さ」によって、4つの区分に分類されます。それぞれの区分には、高さだけでなく周辺環境や構造面での特色があります。ここでは、各区分の高さや技術的特徴、立地環境の傾向について分かりやすくご紹介します。
超高層マンション(タワーマンション)の基準と特徴

超高層マンションとは、一般的に高さ60メートル以上、20階建て以上の建物を指します。日本では、建築基準法により60メートルを超える建築物には厳しい耐震・防災基準が定められており、それに対応した設計や構造が求められます。
超高層マンションの安全性と快適性
超高層マンションでは、制震・免震構造や振動吸収装置(ダンパー)など、日本の耐震基準に対応した技術が用いられています。特に高密度な都心部では、揺れに配慮した設計が取り入れられ、安心感や快適性を考慮した構造となっています。
超高層マンションの周辺環境・立地条件
超高層マンション(タワーマンション)は、都市中心部や再開発が進むエリアに多く建てられており、商業施設や交通機関へのアクセスに優れた立地が魅力です。また、高層階では日当たりが良く、市街地や自然の景色を望めることもあります。
超高層マンションの共用施設

超高層マンション(タワーマンション)には、ジムやラウンジ、ゲストルームなどの共用施設が備わっていることが多く、日常の暮らしをより快適にしてくれます。また、居住者同士が交流できるスペースや、防犯面への配慮がされている点も、多くの方に支持されています。
高層マンションの基準と特徴

高層マンションは、一般的に10~20階建ての建物を指します。超高層に比べて高さは控えめですが、都市部や住宅街に馴染みやすく、都市型の住まいとして広く選ばれています。建設コストが抑えられる一方で、高層階ならではの眺望や採光も期待できます。
高層マンションの安全性と快適性
高層マンションにも、揺れを軽減する耐震・制震技術が取り入れられ、安全面に配慮した設計が施されています。また、風圧対策として強化ガラスや工夫されたバルコニーなど、快適性を高める工夫も見られます。
高層マンションの周辺環境・立地条件

高層マンションは、交通アクセスに配慮した立地に建てられることが多く、都市の利便性を重視する方に選ばれる傾向があります。周辺環境については物件によって異なりますが、住宅街や公園が近いエリアも見られます。
高層マンションの共用施設
高層マンションでは、共用スペースや設備が充実している物件も多く、非常時の備えが考慮された設計も見られます。安心感や利便性を重視する方にとって、選択肢のひとつとなりそうです。
中層マンションの基準と特徴
中層マンションは、一般的に5~10階建ての建物を指します。都市の街並みに調和しやすく、高層マンションに比べて落ち着いた住環境をつくりやすい点が特徴です。
安全性と快適性

中層マンションは、高層建築に比べて構造的な負担が少なく、建設コストを抑えながらも日本の耐震基準に対応した設計が可能です。特に5階建て以上では、耐震や制震構造が採用される例もあり、災害への備えがなされた物件も見られます。また、街の景観と調和する設計が取り入れられることも多く、住みやすさを重視する方にとって選択肢の一つとなっています。
周辺環境・立地条件

中層マンションは、繁華街に近いエリアでは単身者やふたり暮らしの方に、住宅街では子育て世代に選ばれる傾向があり、立地によってさまざまな層に適しています。
ランニングコスト
中層マンションは、建設コストが比較的抑えられる傾向があり、それに伴って管理費や修繕費も控えめな場合があります。ランニングコストを重視する方にとって、選択肢のひとつとなることもあります。特に都市部では、コストを意識した住まい探しの中で検討されやすいタイプです。
低層マンションの基準と特徴
.jpg)
低層マンションは1~5階建ての建物を指し、街並みや自然環境と調和しやすい点が特徴です。階数が少ないため、外出や帰宅の動線が短く、子育て世代や外出の多い方にも使い勝手のよい住まいとされています。
安全性と快適性
低層マンションには、木造や鉄骨構造の建物が多く見られますが、耐震設計が施され、自然災害への備えも考慮されています。また、周辺の緑地や庭園を活かした設計や、街の景観と調和する外観デザインも特徴のひとつです。圧迫感の少ない街並みを好む方にとって、暮らしやすい住環境といえるでしょう。
周辺環境・立地条件

低層マンションは、「第一種低層住居専用地域」などの用途地域に建てられることが多く、静かな住宅街や緑地が保たれやすい環境にあります。こうした地域では建物の高さや用途が制限されるため、周囲と調和の取れた街並みが形成されています。
低層マンションの魅力
低層マンションは、都市計画法に基づく建築制限(用途地域、建ぺい率=敷地に対する建築面積の割合、容積率=延べ床面積の割合)により、周囲との調和を意識した設計が求められます。そのため、建物が周辺環境に与える影響が少なく、落ち着いた街並みが保たれる傾向があります。
それぞれの環境まとめ
| 分類 | 高さの基準 | 技術的特徴 | 周辺環境 | メリット |
| 超高層マンション | 60m以上、20階建て以上 | 制震・免震構造、最新技術 | 都市中心部、再開発エリア | 高眺望、共用施設が充実 |
| 高層マンション | 10~20階建て | 耐震・制震技術採用 | 都市近郊、住宅街 | 日当たり、静かで便利 |
| 中層マンション | 5~10階建て | 耐震設計、コスト抑制 | 街に調和、学校・公園近接 | 管理費・修繕費が低め |
| 低層マンション | 1~5階建て | 木造・鉄骨、耐震設計 | 自然豊か、住宅専用地域 | 緑地多い、地域交流が生まれやすい |
※同じ階数でも構造や周辺環境によって特徴は異なるため、物件ごとの詳細を確認することをおすすめします。
中層・低層・高層など、マンションの種類ごとに異なる特徴があり、ライフスタイルに合わせた選択が可能です。眺望や日当たり、共用施設、立地条件など、さまざまな観点から物件を比較することで、自分に合った住まいを見つけやすくなります。
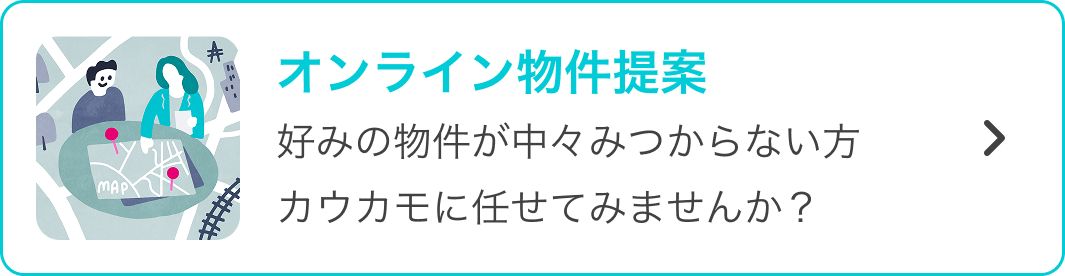

中古・リノベーションマンションの流通プラットフォームに関する知識をわかりやすく提供するため、カウカモ(cowcamo)で日々勉強中。築古マンションの魅力とリノベーションのメリット・デメリットについて深く学び、読者の皆様が最適な選択をできるようサポートしたいと考えています。最新の住宅トレンドや資産価値の維持に関する情報も発信していくので、ご期待ください。

琉球大学大学院理工学部卒。環境建設工学を専攻し、大学院卒業書、建築設計事務所に勤務し、住宅や公共施設など様々な建物の設計に携わる。現在は建築デザイナーとして不動産開発の企画・設計から運営まで行うコンサル会社にて、オフィス設計やリノベーションなどを中心に手がける。趣味は街歩きと珈琲焙煎。空き家を活用して設計事務所と珈琲屋さんを開くことが目標。

















