
床をリフォーム・リノベーションすると、部屋全体の印象が大きく変わります。床は室内で最も広い面積を占めるため、素材や色を変えるだけで空間の雰囲気を一新できます。
築年数の経過やライフスタイルの変化をきっかけに、「そろそろ床を替えたい」と感じる方も少なくありません。工法や使用する床材によって費用や工期は変わるため、あらかじめ特徴を理解しておくことが役立ちます。
この記事では、床材の種類ごとの費用目安や工法・工期の違い、それぞれのメリットとデメリットをわかりやすく解説します。
床のリフォーム・リノベーション工法|張り替えと重ね張り、それぞれの特徴とは?

床のリフォーム・リノベーションには、大きく分けて2つの工法があります。ひとつは既存の床材をすべて撤去して新しく施工する「張り替え」、もうひとつは既存の床の上に新しい床材を重ねる「重ね張り」です。
床下に不具合がある場合は張り替えが必要ですが、状態が良ければ重ね張りも検討できます。工法によって費用や工期が変わるため、事前に特徴を理解して選ぶことが大切です。ここでは、それぞれのメリット・デメリットを整理します。
張り替え工事のメリット・デメリット
◼️メリット
下地の補修が可能
既存の床をすべて撤去して施工するため、床鳴りや沈み込み、劣化など、下地から生じる根本的な不具合にも対応できます。
新築のような仕上がりに
床材を丸ごと新しくすることで、見た目がきれいになるだけでなく、耐久性や快適性も高まり、長く安心して使える空間になります。
床材の選択肢が広がる
厚みや素材の制約がないため、無垢材や防音性の高いフローリング、床暖房対応材など、希望に応じた床材を自由に選ぶことができます。
◼️デメリット
費用・工期ともに負担が大きい
古い床材の撤去や下地処理などの工程が増えるため、施工期間が長くなり、費用も高くなりやすい傾向があります。
生活への影響が大きい
施工中は部屋が使えなくなるため、全室をリフォーム・リノベーションする場合は仮住まいが必要になることもあり、日常生活に影響が出やすくなります。
騒音・粉じんの発生
撤去や施工の過程で騒音や粉じんが発生します。特にマンションでは、近隣への配慮や管理規約による工事時間の確認が必要です。
張り替え工事は、床そのものに不具合がある場合や、住まい全体の耐久性を高めたいときに適しています。
重ね張り工事のメリット・デメリット
◼️メリット
短期間・低コストで施工できる
既存の床を解体せずに新しい床材を重ねるため、工期が短く、費用も抑えられる点が大きなメリットです。
粉じんや騒音が少ない
解体作業がないため、施工中の騒音やほこりが少なく、住みながらのリフォーム・リノベーションやマンションなどでも実施しやすい工法です。
◼️デメリット
床が高くなり段差が生じることも
既存の床の上に新たな床材を重ねるため、床の高さが上がります。ドアの開閉に影響が出たり、段差によって転倒リスクが高まることがあります。特に高齢者がいるご家庭では注意が必要です。
下地の問題は解決できない
下地が劣化している場合でも、そのまま施工されるため、床鳴りや沈み込みといった不具合が残ることがあります。見た目は新しくなっても、根本的な耐久性が向上するわけではありません。
床の状態次第では施工不可
重ね張りは、既存の床が安定していることが前提です。たとえば、反りや浮き、腐食が見られる場合には施工が難しく、張り替え工事が必要になります。
床暖房の導入に制限がある
重ね張りで床暖房を導入するには、対応する床材や工法を選ぶ必要があります。床の高さや断熱性の確保が難しいこともあり、全面的な導入には不向きなケースもあります。
重ね張りは、下地がしっかりしていて、大掛かりな工事を避けたい場合におすすめです。気分転換や部分的な模様替えとしても有効ですが、床の状態によっては専門家の診断が必要です。
床材の種類とリフォーム・リノベーション費用の相場

床をリフォーム・リノベーションする際の床材は、フローリング、フロアタイル、クッションフロアなどから選べます。各床材ごとに耐久性、デザイン性、価格などの特徴があるため、部屋の用途と合わせて総合的に判断して床材を選択するようにしましょう。
フローリング
フローリングは木質系の床材で、無垢フローリングと複合フローリングの2種類があります。それぞれに質感や性能の違いがあり、リフォーム・リノベーションの方法によって費用も変わります。
◼️無垢フローリング
天然木を使用した床材で、木のぬくもりや自然な風合いが楽しめます。調湿性がある反面、湿度の影響で反りが出ることもあり、傷もつきやすい傾向があります。
◼️複合フローリング
合板の表面に化粧材や薄い木材を貼り付けた床材で、反りや変形が起きにくく、耐水性にも優れています。無垢材に比べて風合いに差があるものの、価格やメンテナンスのしやすさが魅力です。
カーペット
カーペットは繊維素材で作られており、防音性や保温性に優れ、色や柄のバリエーションも豊富です。抗アレルギーや難燃加工が施された高機能タイプも多く、DIYで施工できる製品も選べます。
クッションフロア
塩化ビニール素材でできたクッションフロアは、水や汚れに強く、お手入れしやすいことが特長です。キッチンや洗面所などの水まわりに向いており、消臭・遮音などの機能を持つ製品もあります。柔らかい素材なので足腰への負担も軽減されます。
一方で、傷がつきやすく、紫外線や高温で劣化しやすい点には注意が必要です。また、重い家具を置いた部分に跡が残りやすい傾向があります。
床リフォーム・リノベーションの工期

工法や施工面積によって工期は変わりますが、6畳程度の部屋なら、張り替え工事でおおよそ3~4日、重ね張り工事で1~2日が目安です(実際の作業時間のみ)。
ただし、床材の種類や部屋の状態によっては、下地補修や追加作業が必要になり、工期が延びることもあります。工事期間中は該当の部屋が使えなくなるため、家具や荷物は事前に移動し、原則として立ち入りもできません。生活動線や家族のスケジュールを考慮し、余裕をもって準備することが望ましいでしょう。
生活への影響を抑える方法として、部屋ごとに順番に工事を行うか、全体をまとめて一度に工事するかを選ぶことができます。前者は日常生活を保ちながら進めやすく、後者はコストや手間を抑えやすいという特徴があります。
どちらを選ぶかはライフスタイルや床材の状態によって異なるため、自分に合った進め方を検討することが、納得のいくリフォーム・リノベーションにつながります。
床をリフォーム・リノベーションするときの注意点

床下や下地の状態によって、適した工法や工期は変わります。事前に専門家に点検してもらい、その結果に基づいて工法を選ぶことが望ましいでしょう。
工事は日常生活の場で行われるため、騒音や粉じんの発生を想定し、対策を準備しておく必要があります。ペットや小さな子どもがいる場合は、工事中に別室で過ごすなど、落ち着ける環境を確保すると安心です。
マンションなどの集合住宅では、近隣への配慮も欠かせません。管理規約で工事時間が制限されているケースもあるため、事前に管理人や管理組合へ確認しておくことをおすすめします。
また、工事当日には家具や家電を移動する必要があります。大きな家具の移動が難しい場合は、引越し業者などが提供する「家具移動サービス」の利用も選択肢のひとつです。
さらに、季節や天候によって工事の進行が左右されることもあります。仮住まいを伴う大規模なリフォームの場合は、工期に余裕を持ったスケジュールを立てておくと安心です。
まとめ
床のリフォーム・リノベーションは、工法や床材の選び方によって費用や工期が変わります。住まいの状態や生活スタイルに合った方法を選ぶことがポイントです。信頼できる業者に相談しながら、納得のいく計画を立てていきましょう。
また、目先のコストだけでなく、耐久性やメンテナンス性といった長期的な視点を踏まえて判断することで、快適な暮らしにつながります。
中古・リノベーション物件を扱う「カウカモ」では、こだわりの住まいを実現したい方に向けて、“一点もの”の物件を紹介しています。理想の暮らしに近づく第一歩として、ぜひ一度サイトをのぞいてみてください。
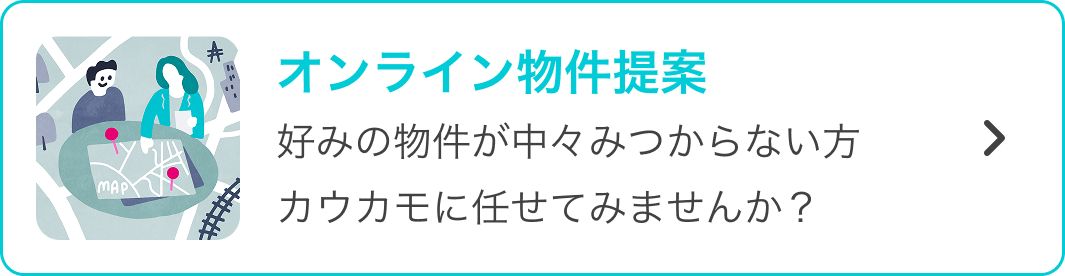

中古・リノベーションマンションの流通プラットフォームに関する知識をわかりやすく提供するため、カウカモ(cowcamo)で日々勉強中。築古マンションの魅力とリノベーションのメリット・デメリットについて深く学び、読者の皆様が最適な選択をできるようサポートしたいと考えています。最新の住宅トレンドや資産価値の維持に関する情報も発信していくので、ご期待ください。

琉球大学大学院理工学部卒。環境建設工学を専攻し、大学院卒業書、建築設計事務所に勤務し、住宅や公共施設など様々な建物の設計に携わる。現在は建築デザイナーとして不動産開発の企画・設計から運営まで行うコンサル会社にて、オフィス設計やリノベーションなどを中心に手がける。趣味は街歩きと珈琲焙煎。空き家を活用して設計事務所と珈琲屋さんを開くことが目標。

















