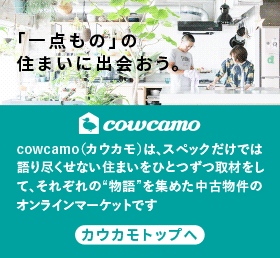中古マンションを購入し、楽しくリノベ暮らしをしているお宅へ訪問インタビューさせていただく「リノベ暮らしの先輩に聞く!」。
今回訪れたのは、大好きな街「蔵前」で中古マンションの一室を購入し、フルリノベーションを施したUさんファミリーのご自宅。仕切りのない開けた生活空間には、同じ時間を過ごす家族への愛情が惜しみなく詰め込まれていた。
■新しい暮らしは、街とともに

浅草からもほど近い蔵前エリア。築36年(取材時)になるマンションの一室は、活気溢れるメインストリートの雰囲気とは真逆の落ち着きある空間が印象的だ
住まいを決めるにあたって、『立地は何よりも重要なポイントだった』と話すご主人。これまで都内で西に東に住む街を変えてきたが、ここ蔵前エリアの特色は “人のよさ” だという。
ご主人:自分たちが住みやすいと思う空間を叶えるだけでなく、住む街にもこだわりたいという想いがありました。
このエリアは先祖代々住み続けている地元の方が多いそうですが、外から来た私たちに対してもみなさん気さくに話しかけてくださるので、とても居心地がいいですね。

冷蔵庫に貼られたマグネットは、お子さまを連れて近所を歩いているときに近所のお店のおじさんがくれたものだそう
■どこに居ても家族に目が届く、開放的な間取りにフルリノベ
住まい作りのきっかけとなったのは、お子さまの誕生。以前の住まいは40㎡ほどだったため家族3人で暮らすには狭く、もっとゆったりと暮らしたいという想いが芽生えたそうだ。
Uさんが新居に求めたのは、ただ面積が広いだけでなく、共に過ごす家族の姿が見て取れるような間取り。そこで、中古マンションを購入してフルリノベーションを施すことに。

玄関から入ってすぐの風景。廊下も仕切りもない、開放感のあるワンルームだ
実は、以前の住まいもワンルームだったそう。お風呂やトイレはガラス張りで、どこにいても家族の気配が感じられたという。奥さまは海外生活を経験する中で、そんなオープンで開放的な間取りが理想の住まいに外せない要素になっていったと話す。

奥さま:新居でも、居住空間をなるべく広くしたかったんです。『廊下は要らないな』『それなら壁も要らないな』という感じでプランニングを進めていったら、自然とこの間取りに落ち着きましたね。
ご主人:この住まい以外にも検討した物件があったのですが、面積がより広いこちらに決めました。3人で暮らすうえで、どうしても55㎡以上は欲しくて。
この物件は70㎡近くあったので、理想を叶えるには十分でしたね。広さがあれば、あとからリノベで自由に空間づくりはできると思ったんです。
注目すべきは、広いワンルームを “上手に使う” ための工夫だ。家族3人分のかさばる寝具や衣類の収納は、小上がりの下やWIC(ウォークインクローゼット)にスマートに収納。
どの家庭でも頭を悩ませる子供の遊び道具は、取り出しやすく片付けやすいオープンラックに収められている。

写真正面は収納を兼ねた小上がりの就寝スペース。右手にあるドアの先は室内窓付きのWIC。どちらも大容量だが、空間を圧迫しない収納だ

リビングはお子さんのプレイスペースでもある。壁沿いに大容量のオープン収納を備えたことで、遊び道具が散らからなくなったそう
さらに床は色違いの塩ビタイルを貼り分け、空間をゆるくゾーニング。このワンルームは「寝る/働く/遊ぶ/食べる/くつろぐ」など、様々な役割をもたせた “マルチルーム” となっているのだ。

塩ビタイルは、お子さまがモノを落としたり家具を引きずっても気にならない機能的な素材だそう。汚れたらその部分だけ張り替えられるので『気が楽になった』と奥さま
■1日中居ても飽きない、こだわりのキッチン
そんな “マルチルーム” のなかで、ひときわ存在感を放つのがフルオーダーのアイランド型キッチンだ。奥さまいわく『家にいることが楽しくなった理由のひとつ』だそうで、ご主人が料理をする機会も増えたという。

キッチンはアイランド型で、シンク側にはL字のカウンターが備わる
ご主人:キッチンは、寿司屋っぽくしたかったんですよ(笑)。
“寿司屋っぽさ” は、できたての料理をすぐに出せるカウンターだけにとどまらない。長時間キッチンに立つことを想定して、お店さながらの使いやすい工夫が凝らしてあるのだ。

天板の高さは、標準的な800〜850mmよりも少し高めの900mmで設計。長時間立っても疲れにくい

シンクにはまな板や水切りをすっぽりとはめ込むことができ、スライドしたり取り外したりとカスタマイズが可能。洗って、切って、並べてがスムーズに行える
奥さま:夫婦そろっての料理はもちろん、友人を招いたときも一緒に作業ができるよう、広めにスペースを取りました。
料理中に娘がキッチンまで来ることも多いですね。道具や野菜の名前をその場で教えてあげることができて、キッチンがリアルな学びの場にもなっています。

カウンターにはコンセントを完備。ご主人はワークスペースとして重宝している。数種類のタイルを貼り分けて、表情豊かに彩った腰壁にもご注目
ご主人:家にいるときは、ほとんどこのキッチンスペースにいます。区切られた書斎よりもオープンな空間の方が居心地がよくて、仕事もここでしていますよ。まわりで妻と娘が遊んでいても、集中しているときは全然気になりません。

シンクの対面には、キッチン用品が収まる大きな収納カウンターが。黒い冷蔵庫の隣にすっぽりと収まっているキャビネットは、ご主人のお父さんが造った思い出の品。収納カウンターの天板は、このキャビネットの高さに合わせて制作された
■スムーズな動線の鍵は、平坦な床
店舗の空間デザインの仕事もされているUさんご夫妻だが、その知見は住まいの空間づくりにも活かされている。ご主人が特に強く意識したのは、生活動線。空間を三次元的に捉えて段差を徹底的になくし、スムーズな室内移動を実現することだ。

写真右手は玄関土間。洗面台の奥に見える扉はWICにつながっていて、外出や帰宅の際に上着を脱ぎ着するのも容易だ
ご主人:“行き止まり” をなくして、回遊性を高めたんです。例えば、玄関横にあるWICは玄関側にも扉を設けて、2方向からアクセスできるようにしています。キッチンも同じ理由からアイランド式を選びました。

シンク部が島のように独立しているアイランド型キッチン。お子さまもペダルカーに乗ってドライブスルーできる
ご主人:回遊性のある室内を移動しやいように、床には極力段差が生じないようにしました。トイレのドアも、床にレールのいらない吊り戸タイプを選んでいます。

唯一段差を設けたのは、玄関土間。洗面台がまたがるように設置されていて、靴を履いたままでも手が洗えて便利なのだそう
また、動線以外でも、各所に使用する部材の選択から照明の色味に至るまで、言われなければ気づかないような細やかなこだわりがそこかしこに。このあたりも、トータルコーディネートが欠かせない商業空間の設計と共通するところだろう。
ご主人:家はとにかくリラックスできる空間にしたいという思いがあったので、冷たい色味の照明は使わないようにしました。日中は窓から十分に陽が入りますし、夜は少し暗くても温かみのある光にしています。

照明はすべて、温かい光で統一

納得のいくものに出会うまで悩み抜いたという玄関土間は、光沢のある人造大理石の一種「テラゾー材」を採用。玄関に明るい印象を与えている
細部まで徹底したこだわりが印象的だが、その背景にはご主人のある哲学があったという。
奥さま:私が住まいづくりで印象的だったのは、主人の予算に対する采配でした。
設備やインテリアの費用で悩んでいた際、『困ったときは一番高いものから削りたくなるけど、こだわりのあるもの、毎日使うものは妥協せず、優先順位の低いものから削ればいいんだ』と話していたんです。
その当時は半信半疑で進めましたが、今は妥協をしなくてよかったと思っています。

家具で妥協しなかったアイテムのひとつが、こちらの「シューメーカースツール」。お尻の型に合わせた台座で座り心地が良く、姿勢も正してくれる優れものだ

ご主人が『絶対に』譲らなかったもののひとつが、意外にもこの真っ黒なトイレ。コストは通常の3倍近くかかったが、白やベージュを中心としたシンプルな空間において、毎日使う設備は黒を中心とした存在感のあるものにしたかったそう
奥さま:毎日使うものは、高くても品質のよいものを選ぶようにしました。家具などは10年、20年と使っていくなかで味が出て、娘が大人になったらヴィンテージ品として引き継げるようにできたらと思っています。
■家族がともに過ごすから、住まいはカラフルになる

お子さまが部屋のあちこちで遊んでいても、その様子を見守ることができる。つかず離れずといった感じで、お子さまに向けるUさんご夫妻の優しい表情が印象的だった
コロナ禍によって家族が共に過ごす時間が増加したいま、住まいの在り方は大きく見直されている。書斎など籠もれる部屋の需要が再び高まるなか、Uさん邸で大切にされていたのは、それとは対象的な「共に過ごす」空間だった。
『これからは、家族でいろいろなカラーを住まいに加えていきたい』とUさんご夫妻は話す。自由に筆を走らせる真っ白な一枚のカンバスのような、“行き止まり” のない家。その暮らしは情緒豊かな街の色も加えながら、さらに色彩を深めていくことだろう。

今後はベランダを活かした家庭菜園にも挑戦したいのだそう
―――――物件概要―――――
〈所在地〉蔵前
〈居住者構成〉3人家族
〈間取り〉1R
〈面積〉69.67㎡
〈築年〉築36年(取材時)
――――――設計――――――
〈会社名〉株式会社coto
〈WEBサイト〉http://coto-inc.net/
取材・撮影:大坪 侑史/編集:清水 駿